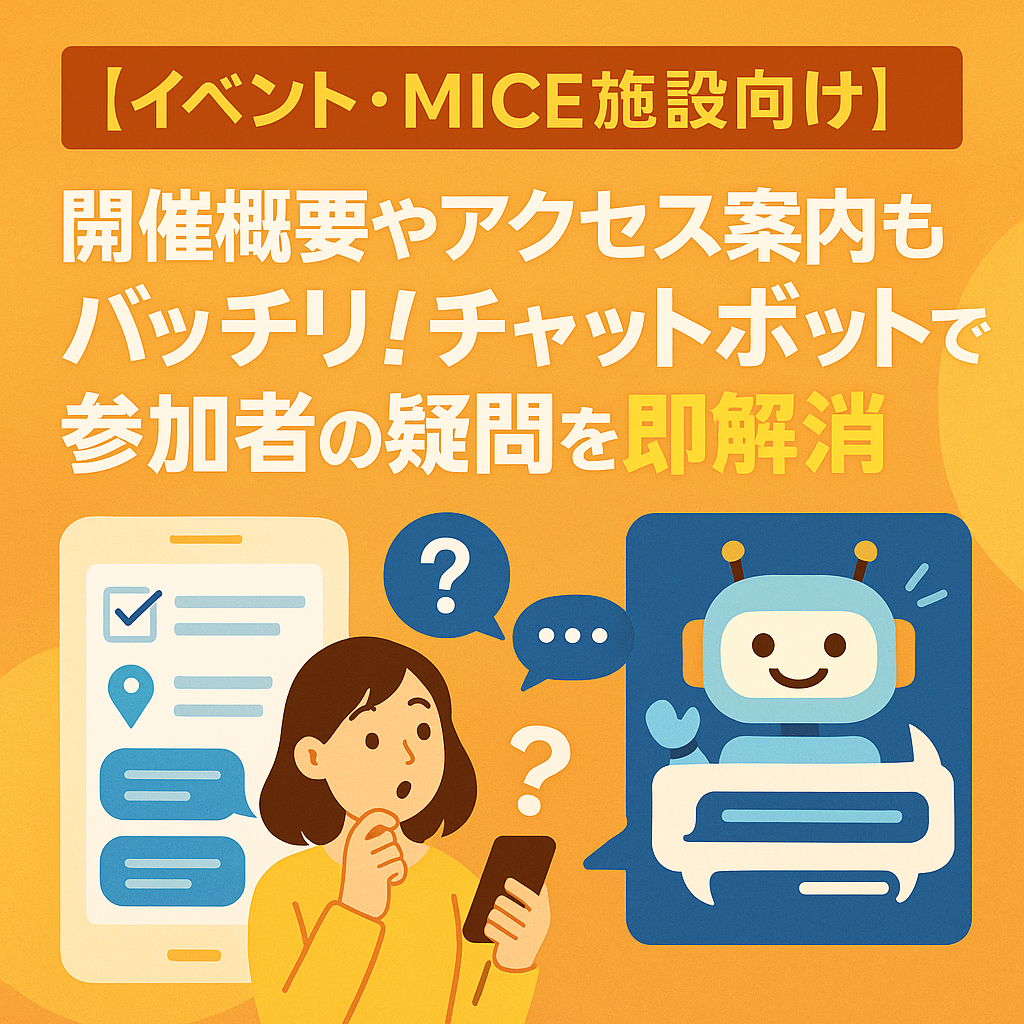鳴りやまない電話、殺到するメール。イベント運営の裏側、見えていますか?
華やかなイベントや国際会議の舞台裏で、運営スタッフの方々がどれほどの奮闘をされていることでしょう。
開催が近づくにつれて、そして当日には、まるで嵐のように押し寄せる参加者からのおといあわせ。
その一本一本、一通一通に丁寧に対応しながら、本来の業務もこなさなければならない現実は、想像を絶する厳しさがあるのではないでしょうか。
「最寄り駅からの行き方は?」
「駐車場は空いていますか?」
「あの講演は何時からですか?」
もし、こうした無数の「お決まりの質問」に、あなたに代わって24時間365日、正確に、そして親切に答えてくれるパートナーがいたら…
そんな、イベント・MICE施設の運営を劇的に変える可能性を秘めた「チャットボット」というかいけつ策について、これからくわしくお話ししていきます。
なぜ今、イベント・MICE施設にチャットボットが求められるのか
「またこの質問…」問い合わせ対応の限界が、すぐそこに
イベント運営におけるおといあわせ対応は、避けては通れない重要な業務です。
しかし、その多くは、事前に告知しているはずの基本的な情報に関するものばかり。
同じ質問に何度も答え続けることは、スタッフの貴重な時間をうばい、心身ともに疲弊させてしまう原因となります。
とくに、イベントの直前や当日は、そのおといあわせが集中砲火のようにやってきます。
電話対応に追われ、本来やるべきだった会場の最終チェックや、登壇者のアテンドがおろそかになってしまう…そんな経験はありませんか。
限られた人員で最高の結果を出すためには、業務の効率化が不可欠なのです。
- 会場へのアクセス方法(電車、バス、車)
- 駐車場・駐輪場の有無、料金、混雑状況
- 開催時間、受付開始時間
- タイムテーブル、プログラムの詳細
- 特定のセッションや登壇者の情報
- 会場内の施設(お手洗い、喫煙所、クローク、授乳室など)の場所
- Wi-Fiの利用方法
- 周辺の飲食店や宿泊施設について
スマホが当たり前の時代。参加者の「知りたい」は待ってくれない
現代のイベント参加者は、スマートフォンを片手に、必要な情報を自分のタイミングで、そして即座に手に入れることに慣れています。
公式サイトのQ&Aページを探したり、電話がつながるのを待ったりするのは、彼らにとって大きなストレスなのです。
知りたいと思ったその瞬間に、まるで友人にLINEで尋ねるかのように、気軽に質問してすぐに答えが返ってくる。
そんなスムーズな体験を提供できるかどうかが、イベント全体の満足度を大きく左右します。
チャットボットは、まさにこの現代のニーズにぴたりとあてはまるコミュニケーションツールといえるでしょう。
イベント体験は「会場に着く前」から始まっている
参加者にとっての「イベント体験」は、会場のドアをくぐった瞬間から始まるわけではありません。
公式サイトで情報を集め、チケットを申し込み、会場へ向かう道のり…そのすべてがイベント体験の一部です。
この「事前体験」の段階で、たとえばアクセス方法が分かりにくかったり、質問への返信が遅かったりすると、参加者の期待値は大きく下がってしまいます。
チャットボットを導入し、参加前のあらゆる疑問や不安を解消してあげること。
それこそが、イベント成功への第一歩であり、最高のおもてなしなのです。
もう慌てない!チャットボットが解決するイベント運営5つの課題
では具体的に、チャットボットはイベント運営におけるどのような課題をかいけつしてくれるのでしょうか。
ここでは代表的な5つのシーンにわけて、その驚くべき実力をご紹介します。
課題①:アクセス案内の達人!参加者を一人も迷わせない
大規模なイベント会場やカンファレンスセンターは、駅から少し離れていたり、入口が複数あったりと、初めて訪れる人にとっては分かりにくいもの。
「会場にたどり着けない」というおといあわせは、運営側にとっても参加者側にとっても、大きな負担となります。
チャットボットは、このアクセス案内を驚くほどスマートにかいけつします。
たとえば、チャットボットのメニューに「アクセス」というボタンを用意し、タップすると「電車でお越しの方」「お車でお越しの方」といった選択肢が表示されるようにします。
「電車」を選ぶと、最寄り駅からのルートが写真付きで表示されたり、案内動画が再生されたり…
これなら、土地勘のない方でも安心して会場までたどり着けるはずです。
さらに、複数の入場ゲートがある場合でも、チケットの種類(例えば「VIP」「一般」「プレス」など)に応じて、どのゲートへ向かえばよいかを自動で案内することも可能です。
「自分の入り口はどこだろう?」という参加者の不安を解消し、スムーズな入場をうながすことで、受付周辺の混雑緩和にもつながります。
課題②:「あの講演は?」プログラムに関する質問を完全自動化
数多くのセッションや講演が同時に進行するカンファレンスや展示会。
「お目当てのプログラムは何時からだっけ?」「場所はどのホール?」といった質問は、ひっきりなしに寄せられます。
チャットボットを使えば、分厚いパンフレットをめくらなくても、手元のスマートフォンでいつでも最新の情報を確認できます。
「タイムテーブル」「登壇者一覧」といったメニューはもちろんのこと、「基調講演」や「〇〇氏」といったキーワードで検索すれば、関連する情報がすぐに表示されるように設定することも可能です。
さらに便利なのが「リマインド機能」です。
参加者が気になるプログラムを事前にお気に入り登録しておけば、開始10分前などに「まもなく〇〇が始まります」といったプッシュ通知を送ることができます。
この細やかな心くばりが、参加者の「聞き逃した…」という残念な思いを防ぎ、満足度を飛躍的に高めるのです。
課題③:広大な会場の案内人!「お手洗いはどこ?」にも即答
展示場や大規模なホールは、まるで迷路のよう。
「お手洗いはどこですか?」「喫煙所はありますか?」「クロークに荷物を預けたいのですが…」
こうした会場内の施設に関する質問は、インフォメーションカウンターに集中しがちです。
チャットボットを「会場のデジタル案内人」にしてしまいましょう。
「フロアマップ」メニューを用意し、参加者が目的の施設をタップすると、現在地からのルートがマップ上に表示されるようにすれば、もうスタッフが口頭で説明する必要はありません。
展示会であれば、出展している企業のブース場所や、その企業がどんな製品を展示しているのかといった詳細情報まで案内することができます。
参加者の利便性を高めるだけでなく、出展企業の満足度向上にも貢献できる、まさに一石二鳥の活用法です。
課題④:イベント滞在をまるごと支援するコンシェルジュに
イベントに参加する人の興味は、イベントそのものだけにとどまりません。
「お昼を食べるのにおすすめの場所は?」「近くにコンビニはありますか?」「このあと懇親会で使えるお店を知りたい」など、周辺情報に関するニーズも非常に高いのです。
チャットボットに、こうした周辺情報をあらかじめ登録しておきましょう。
「ランチ」「カフェ」「居酒屋」といったカテゴリーにわけて、おすすめのお店のリストを地図付きで表示できるようにしておけば、参加者は休憩時間やイベント後も、ストレスなく過ごすことができます。
提携している駐車場や、近隣のコインパーキングの満車・空車情報などをリアルタイムで提供できれば、さらに喜ばれることでしょう。
イベント本体だけでなく、その周辺の体験価値まで高める。それが、これからの施設運営に求められる「おもてなし」の姿ではないでしょうか。
課題⑤:急な変更にも即応!頼れるリアルタイム情報発信基地
イベントにトラブルはつきものです。
登壇者の到着が遅れてプログラムの開始時間が変更になったり、悪天候で一部の屋外企画が中止になったり…。
こうした急な変更情報を、いかに迅速かつ正確に参加者全員に伝えられるかが、運営の手腕を問われるところです。
チャットボットのプッシュ通知機能を使えば、重要な変更事項を参加者のスマートフォンに一斉に、そして瞬時に届けることが可能です。
ウェブサイトのお知らせを更新したり、会場でアナウンスをしたりするよりも、はるかに確実でスピーディーな情報伝達が実現します。
また、忘れ物や落とし物の問い合わせ窓口としてチャットボットを活用することも有効です。
災害発生時などの緊急連絡手段としても、その威力は絶大。チャットボットは、平時だけでなく有事の際にも、運営を支えるきわめて頼もしい存在となるのです。
導入しない手はない!チャットボットがもたらす感動のメリット
チャットボットを導入することで、具体的にどのような素晴らしい変化が訪れるのでしょうか。
ここでは、運営側、参加者側、そして主催者側の三方にとってうれしい、感動的なメリットをくわしく解説します。
メリット①:問い合わせコスト激減!スタッフは「おもてなし」に集中できる
もっとも直接的で分かりやすいメリットは、やはり「コスト削減」です。
これまで電話やメールの対応に追われていたスタッフの人件費や、イベントのために臨時で雇っていた派遣スタッフの費用を、大幅に削減することが可能になります。
ある施設では、チャットボット導入後、おといあわせの電話が8割以上減ったという事例もあるほどです。
しかし、本当の価値は、単なる経費削減にとどまりません。
定型的な質問対応から解放されたスタッフは、人でなければできない、より質の高い「おもてなし」に集中できるようになります。
困っている様子の参加者に自分から声をかけたり、会場の雰囲気を盛り上げるための企画を考えたり…。
スタッフの働きがいを高め、イベント全体の質を向上させる、という大きな副産物をうむのです。
- 単純作業から解放され、精神的なストレスが減る
- 本来の専門業務や、より創造的な仕事に時間を使える
- 参加者と直接向き合う時間が増え、やりがいを感じられる
- 残業が減り、ワークライフバランスが改善する
メリット②:参加者の満足度が上がり、イベント評価もうなぎのぼり
参加者にとってのメリットは、なんといっても「ストレスフリーな体験」です。
知りたいと思ったその瞬間に、24時間いつでも、多言語で、正確な答えが手に入る。
この「当たり前のようで、これまで当たり前ではなかった」体験は、参加者に深い満足感と感動をあたえます。
とくに、海外からの参加者が多い国際会議などでは、多言語対応チャットボットの存在は絶大です。
言葉の壁を気にすることなく、自国の言葉でスムーズに情報を得られる安心感は、何物にも代えがたい価値があります。
こうしたポジティブな体験は、「このイベントは参加者に親切だ」「運営がしっかりしている」という高い評価につながります。
SNSなどでの好意的な口コミをうみだし、それが次回のイベントへの集客へとつながっていく…そんな理想的なサイクルが生まれるのです。
メリット③:主催者からの信頼を獲得!イベント誘致の強力な武器になる
MICE施設の運営者にとって、イベントを主催してくれる企業や団体は、大切なお客様です。
主催者は、自分たちが企画したイベントを成功させるために、サポートが手厚く、信頼できる施設を選びたいと考えています。
「私たちの施設では、参加者サポートのために専用のチャットボットをご用意できます」
これは、他の施設との差別化を図るうえで、きわめて強力なアピールポイントとなります。
主催者が懸念するであろう、参加者からのおといあわせ対応という大きな負担を、施設側がかいけつ策として提示できるのです。
「あの施設にまかせれば、参加者対応も安心だ」という評判が広まれば、おのずとあなたの施設は主催者から選ばれる存在になるでしょう。
チャットボットは、守りの業務効率化ツールであると同時に、施設の価値を高め、新たなビジネスチャンスを呼び込む「攻め」のツールでもあるのです。
初めてでも大丈夫!イベント向けチャットボットの選び方・育て方
「チャットボット、ぜひ導入してみたい!でも、何から手をつければいいの?」
ご安心ください。最近では、ITの専門知識がない方でも、かんたんに導入・運用できるサービスが数多く存在します。
ここでは、あなたのイベントを成功にみちびくための、チャットボットの選び方と、導入後の育て方について解説します。
失敗しない!チャットボット選び、3つの鉄則
鉄則①:イベント特有の機能はそろっているか?
チャットボットには様々な種類がありますが、まず確認すべきは「イベント利用」に特化した機能があるかどうかです。
たとえば、イベントの開催期間だけチャットボットを有効にする「会期設定機能」や、急な変更をリアルタイムで告知できる「一斉通知機能」などは、イベント運営において必須といえるでしょう。
また、イベントごとに質問内容が大きく変わるため、過去のイベントで作成したシナリオ(会話の台本)をテンプレートとして保存し、次のイベントでかんたんに再利用できる機能があると、運営の手間を大幅に削減できます。
鉄則②:シナリオ作成は、誰でもかんたんにできるか?
チャットボットの「賢さ」は、シナリオの質にかかっています。
このシナリオを、専門家でなくても直感的に、そしてスピーディーに作成・修正できるかどうかは、きわめて重要な選択基準です。
管理画面が分かりやすく、まるでブログを書くような感覚でQ&Aを追加したり、会話の流れを組み立てられたりするサービスを選びましょう。
無料トライアルなどを活用して、実際に操作感を試してみることを強くおすすめします。
鉄則③:料金体系は明確で、柔軟性があるか?
料金体系は、チャットボットサービスを選ぶうえで見逃せないポイントです。
とくにイベント利用の場合、年間契約だけでなく、数日間や一ヶ月といった「短期間利用」が可能なプランがあるかどうかを確認しましょう。
特定のイベント期間中だけ利用したい、というニーズに柔軟に応えてくれるサービスが理想的です。
初期費用はいくらか、月額費用はどのくらいか、そしてその料金で何人のスタッフが管理画面を操作できるのか、何件までのおといあわせに対応できるのかなど、細部までしっかりと比較検討することが、のちの満足につながります。
わずか3ステップ!あなたのイベントを成功にみちびく導入術
チャットボットの導入準備は、実はイベントの成功に向けたシミュレーションそのものです。
以下の3つのステップで、参加者にとって最高の案内人を作り上げていきましょう。
- 分析:過去のイベントの問い合わせ履歴を分析し、「よくある質問リスト」を作る。
- 設計:参加者の気持ちになって、分かりやすく、楽しい会話のシナリオを設計する。
- 訓練:本番前にスタッフ全員で参加者役になってテストし、改善点を見つけ出す。
ステップ①:過去の「声」に耳をすませ、質問を洗い出す
まずは、過去のイベントで寄せられたおといあわせのメールや、電話対応の記録を掘り起こしてみましょう。
そこには、参加者が何に困り、何を知りたいと思っているのか、という貴重な「生の声」が眠っています。
「アクセス」「プログラム」「会場施設」などのカテゴリーに分類しながら、想定される質問をすべてリストアップしていく作業が、すべての土台となります。
ステップ②:参加者の心になって、シナリオを組み立てる
リストアップしたQ&Aを、チャットボットに登録していきます。
このとき大切なのは、「単なる一問一答」で終わらせないことです。
たとえば、「駐車場はありますか?」という質問に対して、「はい、ございます」と答えるだけでは不十分です。
「はい、ございます。料金は〇〇円で、現在の空き状況はこちらです」と答え、さらに「駐車場の地図を見る」「他の交通手段を見る」といった選択肢ボタンを表示するなど、参加者が次に知りたいであろう情報を先回りして提示してあげましょう。
少しのユーモアを交えるなど、親しみやすいキャラクター設定を考えるのも楽しいかもしれません。
ステップ③:本番前のリハーサルで、最高の案内人に
シナリオが完成したら、本番前に必ずリハーサルを行いましょう。
運営スタッフが参加者役になりきって、実際にチャットボットを使ってみます。
「この説明は分かりにくいな」「こんな質問をされたら答えられないぞ」「この画像のほうが親切だ」など、たくさんの改善点が見つかるはずです。
このプロセスを丁寧に行うことで、チャットボットの精度は格段に向上します。
イベント本番では、自信をもって参加者に提供できる、頼もしい案内人が完成していることでしょう。